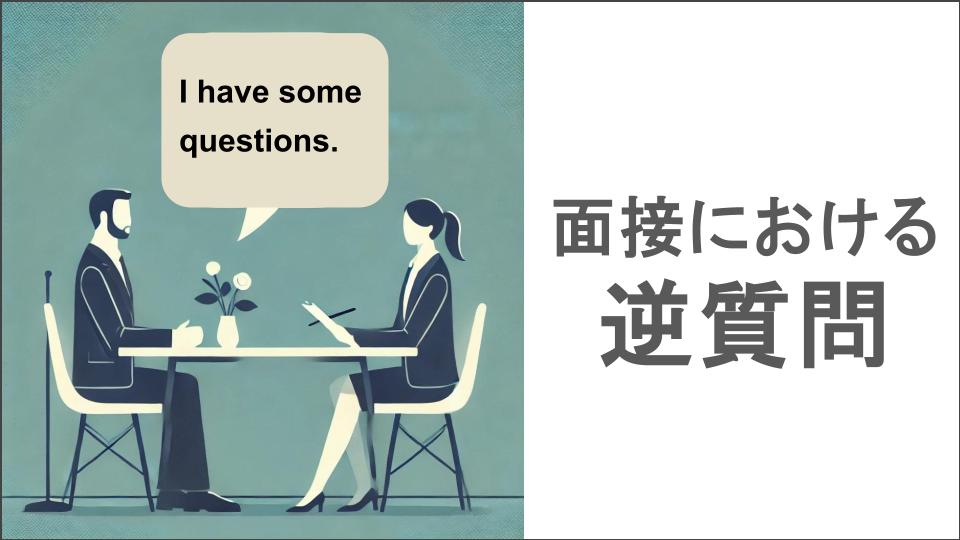面接の時間内に逆質問が設けられる機会も多いと思う。当社も基本的には必ず最後に逆質問を設けるような設計をしている。逆質問は面接の最後のタイミングになることが多いので、多少なりともその方の印象に結びつきやすい要素であるが「この時間をどのように活用すればよいか」「どのようなことに注意して逆質問を行うべきか」など、悩む方もいらっしゃると思う。そこで今回の記事では面接における「逆質問」触れてみたい。
逆質問はほとんど結果に影響しない
まず覚えていてほしいのは逆質問と面接結果の関連についてだが、逆質問のタイミング(面接の最後)までにはすでにその面接の評価が決まっていることの方が多いので、逆質問の時間で評価に影響を及ぼすことは難しい。特に、面接の評価が低い状態のものを逆質問の時間でプラスに持っていくことはほぼ不可能である。一方、これまでの面接評価は良かったものの、逆質問の内容によっては少し評価を下げてしまう可能性はありうる。その点は意識をした上で、下記内容を確認してみてほしい。
逆質問で避けた方が良い内容
特にNG質問というものはないのだが、逆質問を受ける立場からみてあまり良い印象にはならない内容をいくつか挙げたいと思う。

調べたら分かる内容
せっかく逆質問を通して情報が取れる時間なので、調べたら分かるようなことは聞かない方が無難である。質問される側としても、最低限それぐらいは調べてもいいのでは、、、と感じることがある。例えば、よくあるのが「求める人材像を教えてください」や「今後注力すべき事業分野」などが挙げられる。これらは採用HPや中期経営計画に掲載されていると思うので、まずは知識として頭に入れた状態を作った上で、「採用HP上で⚫︎⚫︎を求める人材像として掲げられていますが、▲▲さん(面接官)はどのような場面でこの素養が求められると思いますか」とか「中期経営計画上で⚫︎⚫︎の分野に注力すると記載されていますが、社内では具体的にどのような活動を行なっていますか」といったような形でその先の質問へと繋げていくと良い。
面接官に直接関係のない内容
実際にあった例としては「以前のインターンシップの交通費がまだ振り込まれておりませんが、いつ頃支給されますか」「仮に今回の面接を通過した場合、次の面接予約はいつから始まりますか」「入社後の研修のスケジュールや内容を教えてください」などが挙げられる。面接官全員が採用業務全般やインターンシップ、入社後の研修の中身全てを把握しているわけでない。上記の質問例は採用担当に直接問い合わせするべき内容だと思うので、逆質問の時間に含めない方が良いだろう。
面接のフィードバックを求める内容
今回の面接を通じて自分がどのように映ったか気になるのは当然だが、面接の逆質問の場でそのフィードバックを求めることは避けた方がよい。人事部員や採用担当などの面接慣れしている人間であれば、フィードバックを求める質問にもある程度対応ができることもあるだろうが、面接官は人事部員だけではなく各部門から選出された社員が担当することも多いため、相手を困らせてしまうことになる。加えて面接の結果は多かれ少なかれその方の人生に影響を与えるものでもあるため、面接官もそんなに簡単に言葉にできるものではない。もし本当に面接のフィードバックが欲しい場面があれば、採用担当に相談してみると良いだろう。面接官直々ではないにしろ面接官の残した評価内容を共有してもらえるケースはあるだろう。
待遇や福利厚生に絞った内容
最終的に会社を選ぶ上で待遇や福利厚生は外せない要素なので、然るべきタイミングでは必ず確認すべき点だと思う。しかし、面接最後の逆質問の時間にこの内容にフォーカスされてしまうと面接官側もやはり複雑な気持ちになる。また待遇や福利厚生も時代背景等に合わせて変化するものなので、面接官自身が十分な知識を持ち合わせていないことも考えられる。したがって、待遇や福利厚生などの情報は各種イベントの質疑応答や内々定が出た後などの然るべきタイミングで、然るべき担当者(採用担当が望ましい)に確認することをおすすめする。
逆質問で投げかけてみてほしい内容
避けた方がよい内容は上記の通りであるが、逆質問を通じて有益な情報を取得できる可能性もあるので、下記内容を参考にして自分なりに質問内容を考えてみてほしい。

自分の考えを含めた質問内容
その企業に関する基本的な情報を頭に入れた上で、自分なりに思考を巡らせて出てきた質問などは良い印象を持たれることがある。例としては次のような内容だ。
- 業界における御社の強みは⚫︎⚫︎と捉えていますが、実際に現場でも強みと認識されていますか?
- 将来的には⚫︎⚫︎といったトレンドが強まると思いますが、その中での御社の成長戦略はどのようなものでしょうか?
- 将来的には⚫︎⚫︎のような人材が求められると考えていますが、御社でもこのような人材は求められると思いますか?
企業やその企業が属する業界情報はいろいろなところから取得できるが、それらを一度自分の中で整理した上で質問を考えてみると良いだろう。
その企業に求められる素養関連の質問
この質問内容は入社後のイメージを明確することに加え、相手に興味があることを伝えることにも繋がるためおすすできる。例としては次のような内容だ。
- 御社で活躍されている方の特徴を教えてください
- 御社のビジネスを推進していく上で、必要になるスキルや知識を教えてください。
- 社員共通で持っているマインドや仕事への取り組み方などがあれば教えてください。
その企業で働くイメージを強化できるように質問に織り交ぜてみるのも良いだろう。
面接官の経験や考えに触れる質問
一昔前は面接官が自分の名前や属性を明かさない時代もあったが、最近は面接官も自己紹介をしてくれる企業が多くなっていると思う。面接官の属性もさまざまだとは思うが、これまでのキャリアの中で培ってきた経験値や仕事の中で大切にしていることがあると思うので、その部分に対して質問すると有益な情報や参考になる情報が取得できる可能性が高い。またその回答の温度感や内容でその企業の社員の性質なども知ることができるだろう。
- ⚫︎⚫︎さんは、事業本部で新規ビジネスの企画を担当されているかと思いますが、その中で大切にしているマインドや仕事のステップなどがあれば教えてください。
- ⚫︎⚫︎さんは管理職としてメンバーのマネジメントにも従事されている立場かと思いますが、人材マネジメントにおいて意識されていることを教えてください。
- 今までの仕事の中で特に印象に残っている仕事を教えてください。
面接官も人なので、自分のことに興味を持ってくれることは嬉しいことだと思う。有益な情報にアプローチできるように面接官自身に対する質問も投げかけてみてほしい。
逆質問は2〜3個用意しておこう
上記の内容を踏まえ、逆質問は2〜3個を目安に自分の聞きたいこと中心にまとめておいてほしい。注意点としては、面接の状況などを伺いながら投げかける質問数を調整することだ。面接日はタイトなスケジュールを組んでいる場合も多いので、5個も6個も質問を投げかけてしまうと次の面接に影響を及ぼすしかねない。面接官と会話しながら適切な量と質の逆質問を投げかけることで、新たな発見や企業に対する見極めに繋げてみよう。
本記事をご拝読いただきありがとうございました。