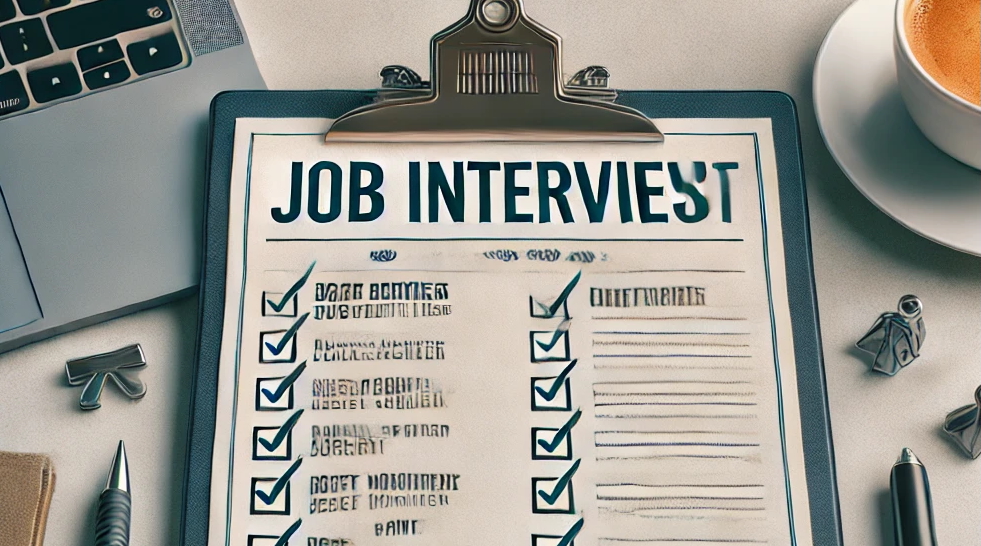就職活動において、企業側は就活生の何を確認しているのか。おそらく多くの就活生が気になる点だと思う。もちろん企業ごとに異なる点はあるが、主軸は大きく変わらないと考えている。それは「能力(スキル)」と「適正」の二点である。就活生はこの前提を認識した上で就職活動を進めてほしい。本記事では企業側が確認しているこの二点について深掘りしてみたいと思う。
確認ポイント1:能力(スキル)
一言で「能力」といってもどのような力が求められているのか難しいところだと思う。大別すると下記のような「汎用的な能力(スキル)」と「専門的な能力(スキル)」に分類することができる。
| 汎用的な能力(スキル) | 専門的な能力(スキル) |
| ・コミュニケーション力 −対人対応力(関係性構築力やストレス耐性など) −文章力(ライティングスキル) −交渉力 −傾聴力 など ・論理的思考力(構造的に考える力や判断する力) ・行動力(巻き込む力、結果に繋げる力) ・タイムマネジメント力 ・ITリテラシー など | ・語学力 ・プログラミングスキル ・マーケティングスキル ・財務および会計関連スキル ・人事労務関連スキル ・データ分析や統計学関連スキル ・デザインスキル(Webデザインなど) など |
社会人以降で目指すべき人材像としては「T型人材(汎用的なスキル+専門的なスキルを持つ人材)」や「π型人材(汎用的なスキル+専門的なスキルを複数持つ人材)」であることはよく言われることだ。私も含めて特にπ型の人材を目指したいところだが、メンバーシップ型の採用が主流の日本の新卒採用市場では、まず優先されるのは「汎用的なスキル」だと思う。ジョブ型採用を実施している企業や、専門職の採用コースを設けている企業では専門的なスキルを重視されることはもちろんあるが、どれだけそのスキルが高くとも、汎用的なスキルが欠如している場合は合格に至らないケースもある。したがって、汎用的なスキルをまずは磨きつつ、自分に適正のある専門的なスキルも育てていこう。また「汎用的な」スキルと言えども、それを突き詰めると専門性を帯びてくる。例えば、「どんな人間とでも友好関係を構築できる対人対応力」や「本質的な課題を形成できる論理的思考力」、「誰にでも共通理解をさせることができる文章力」などである。誰かに褒められるような、真似したいと思われるようなレベルを目指して汎用的なスキルを磨いてみてほしい。
確認ポイント2:適正
ここでいう適正とは、その個人が組織に対してどのぐらいマッチングしているかを指している。この適正については「個人→組織」と「組織→個人」の両方のベクトルが存在する。こちらも表で簡単にまとてみた。
| 個人→組織の適正 | 組織→個人の適正 |
| ・組織の理念や方向性に共感できているかどうか ・組織の文化や雰囲気に適応できるかどうか ・組織の提供価値に納得できるかどうか など | ・個人の各種希望を組織内で実現できるかどうか −待遇や働き方 −職種やキャリアビジョン など |
この両方のベクトルが合わないと、能力が伴っていても合格を出せないこともある。例えば、個人の希望に「20代で2000万稼げるようになりたい」というものがあったとしても、その組織ではどう頑張っても1000万円が限界、、、といったケースだ。こういったミスマッチは早期退職につながるケースも多く、双方にとって時間とコストの無駄になってしまう。この点は認識した上で就活を進めていただきたい。特に最終面接等の後半の面接で結果が伴わなかった場合は、能力というより適正がなかったと割り切って切り替える気持ちも重要だ。
この「適正」について、就活生の皆さんとしては内定を勝ち取りたいが故に多少無理して組織の価値観や考え方に合わせようとしてしまうかもしれないが、採用担当としてはおすすめはできない。もちろん全てが自分に適した組織はないので、許容できる範囲を決めて合わせにいくことは大切であるが、自分が一番譲れないポイントは自分の考えや価値観を貫いてほしい。その結果内定を勝ち取ることができた企業が自分と親和性の高い組織であり、社会人の一歩を踏み出し易くなるだろう。
以上、就職活動において企業が確認している二つのポイント「能力(スキル)」と「適正」についてまとめてみた。一般的な内容をベースに記載したが、その組織でどのようなスキルや適正が大切にされているのかは各種採用イベントに参加し、採用担当や社員とコミュニケーションをとりながら明確化していく必要があることは忘れないでほしい。
今回の記事が就活生の一助になれば嬉しく思う。
本記事をご拝読いただきありがとうございました。